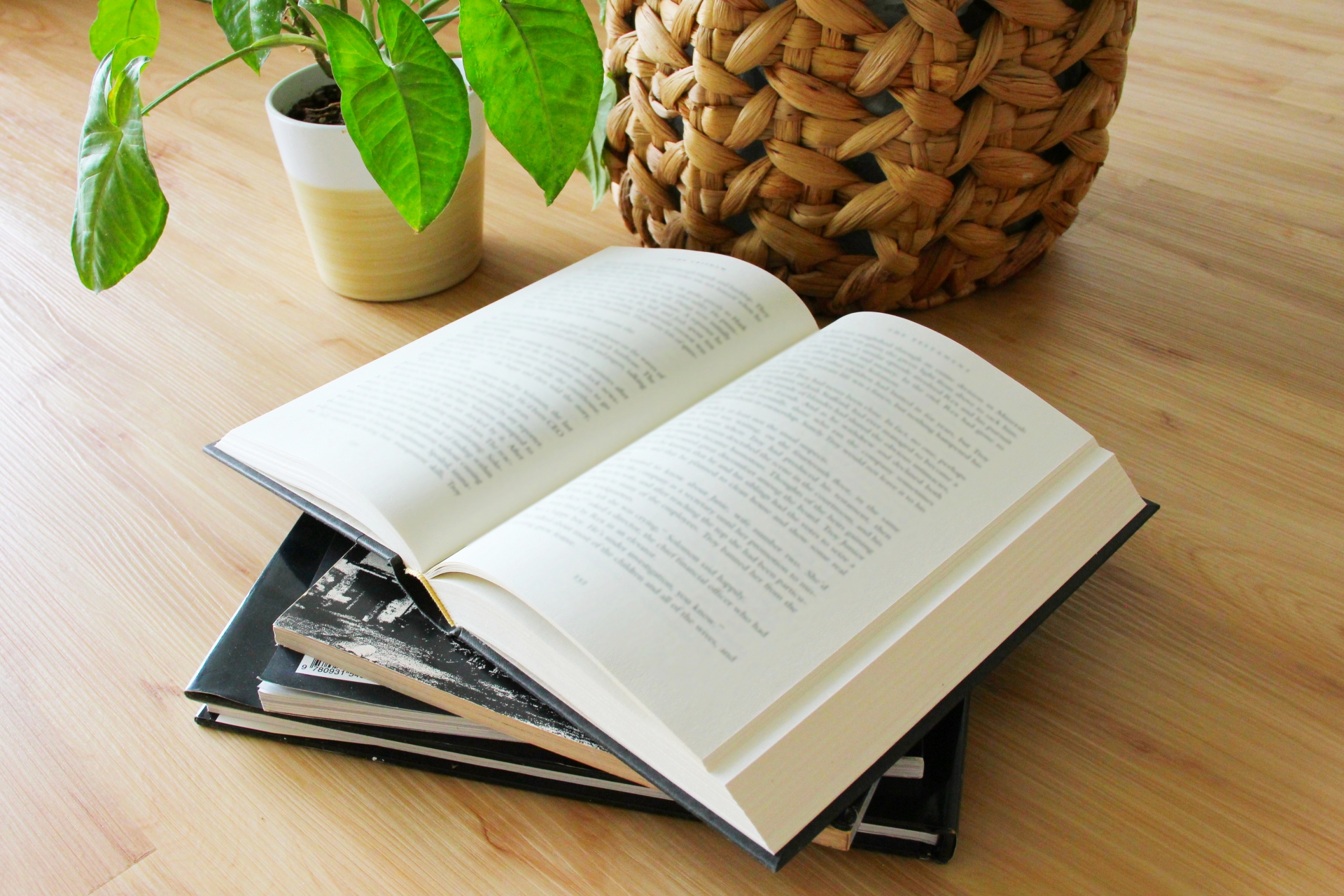読書をしたいと思って本を買ったのに、気づけば読まずに積んでしまう。そんな経験、ありませんか?
本を読むこと自体は嫌いじゃない。むしろ好き。だけど「時間がない」「集中できない」「ついスマホを触ってしまう」。そんな理由で、なかなか読書が習慣にならない人は少なくありません。
この記事では、忙しい日々の中でも読書の趣味を続けるコツや、読書習慣のつくり方を紹介します。本を読むことがもっと気軽で、楽しいものになるきっかけになれば幸いです。
読書を趣味にするメリット

読書を「続けなければならないもの」ではなく、「趣味」として捉えられるようになると、本との距離はぐっと近づきます。義務感から解放され、自分のペースで向き合えるようになることで、読書の時間そのものが心地よいものに変わっていきます。
ここでは、読書を趣味として楽しむことで得られる、日常の中での小さな変化や魅力について見ていきましょう。
情報だけでなく“気持ち”が整う
読書には、ただ知識を増やすだけではない深い魅力があります。ページをめくるたびに、物語の世界に入り込んだり、登場人物の気持ちに寄り添ったり。
その静かな時間の中で、自分の中のざわめきが少しずつ落ち着いていくのを感じることがあります。
忙しい毎日の中では、ついスマホの通知や仕事のことに追われてしまいがちですが、本を開くと、時間の流れがゆるやかになり、言葉の一つひとつが、心の奥をやさしく撫でてくれる感覚があります。
読書とは、情報を取り込む行為であると同時に、自分の気持ちを静かに整える大切なひとり時間でもあります。
時間の使い方に満足感が生まれる
SNSや動画を見て過ごす時間も、気分転換としては悪くありません。けれど、1冊の本を読み終えたときに感じる充実感は、それとは少し違います。それは「何かを終えた」という達成感だけでなく、自分の中に新しい何かが芽生えたような感覚。
本を閉じたあとに残る余韻や、ふとした気づきが、心に静かな余白をつくってくれます。「自分のために良い時間を使えた」と思えることは、日々を豊かにする小さな自信にもつながります。
たとえ数ページでも、寝る前の10分でもかまいません。ほんの短い読書の時間が、日常の中に満足感と落ち着きを運んでくれるはずです。
読書が続かない理由あるある

「読書が続かない」と感じると、つい自分の意志の弱さや集中力のなさを責めてしまいがちです。
けれど、読書が習慣にならない理由は、特別なことではなく、誰にでも起こりやすいものばかりです。
ここでは、多くの人がつまずきやすい「読書が続かない理由」を整理しながら、気持ちを少し楽にするヒントを探していきます。
時間が取れない
読書が続かない理由のひとつに、「まとまった時間がないと読めない」と思い込んでしまうことがあります。でも実際には、1日10分でも、寝る前のほんの数ページでも十分です。
コーヒーを淹れる間や、通勤電車の中、待ち時間の5分でも、本を開けばそこは小さな読書の世界。「少しだけ読む」を積み重ねていくことで、気づけば1冊を読み終えていた…なんてこともあります。
大切なのは、量ではなく“本を開く習慣”を持つこと。「時間がない」ではなく、「今の自分にできる時間で読む」と考えると、読書はぐっと身近になります。
本を選ぶのに疲れる
最近は本の種類も多く、気になるタイトルが次々と目に入りますよね。あれもこれもと迷っているうちに、結局どれも読まずに終わってしまう。そんな“本選び疲れ”を感じたことがある人も多いのではないでしょうか。
また、「話題だから読まなきゃ」「この本を読まないと遅れてる気がする」といった義務感で選んでしまうと、読む前から気持ちが重くなってしまいます。
迷ったときは、「今の気分に合うもの」「読みやすそうなもの」から手に取ってみましょう。
雑誌のコラムやエッセイでも立派な読書です。“読むことを楽しむ”ことを思い出せば、自然と本との距離も近づきます。
内容を忘れるのが不安
「せっかく読んだのに、内容を覚えていない」「メモを取らないと意味がない気がする」そんなふうに感じて、読書が“勉強”のようになってしまうこともあります。
けれど、本はすべてを覚えておくために読むものではありません。その瞬間に感じた言葉の響きや、心が少し軽くなった感覚こそが、読書の一番の価値です。
読んだ内容は忘れても、心に残った“印象”は確かに自分の中に残ります。だから、肩の力を抜いて「読む時間そのものを楽しむ」気持ちで十分。思い出せなくても、その本を読んだ“心の記憶”はちゃんとあなたの中に息づいています。
時間がない人のための読書習慣づくりのコツ

忙しい毎日の中で、「読書の時間を確保しなければ」と考えると、それだけでハードルが高く感じてしまうことがあります。けれど、読書はまとまった時間がなくても、少しずつ積み重ねていくことができます。
ここでは、時間に余裕がない人でも取り入れやすい、無理のない読書習慣のつくり方をご紹介します。
読書を続けるコツ
読書を続けるために大切なのは、「完璧にやろうとしないこと」。1日数ページでも、気になるところだけ読んでもOKです。
「読まなきゃ」ではなく、「読みたいときに開こう」と思える気持ちの余裕が、長く続ける秘訣です。
“ながら読書”も立派な読書
読書というと、机に向かって静かに読むイメージがありますが、もっと気軽で大丈夫。たとえば、カフェでコーヒーを飲みながら、音楽を聴きながら、寝る前のベッドの中で。少しのスキマ時間にページをめくるだけでも、心は十分満たされます。
もちろん紙の本でも、電子書籍でもOK。いつでも読めるようにしておけば、「思いがけない空き時間」を読書タイムに変えられますし、スマホに読書アプリを入れておけば、出先で1ページだけでも読むことができます。
「ながら」でも書籍に触れることで、言葉が自然と日常に溶け込んでいきます。
“読みたい”と思える環境をつくる

お気に入りのしおりや、読みかけの本を置く小さなスペースをつくってみると、「また続きが読みたい」と思えるきっかけになります。
照明の明るさや座る場所を変えるだけでも、読書時間がぐっと心地よくなります。ベッドサイドや窓辺、リビングの片隅など、自分だけの“読書スポット”を見つけてみましょう。
途中でやめてもいい
読書は「完走すること」が目的ではありません。最後まで読み切ることにこだわらなくても大丈夫。「合わないな」「今日は気分じゃないな」と感じたら、そこでいったん閉じてもOKです。
読書は義務ではなく、心を自由にする時間です。読んでいて楽しい、心地いいと思える本を読むことが、習慣化の一番の近道です。
本との出会いにはタイミングがあります。しばらくしてまた手に取ったとき、「あのときよりもスッと心に入ってくる」と感じることもあります。大切なのは、“読むことを楽しむ心”をなくさないことです。
小さな積み重ねが、自分をつくる
1冊を読み終えたときの達成感も素敵ですが、何よりも価値があるのは、「今日も少し読めた」という積み重ね。
ページをめくるたび、言葉や感情が少しずつ自分の中に染み込み、それが知らず知らずのうちに、考え方や感じ方を豊かにしてくれます。
読書は、目に見えないけれど確かに“自分を育てる時間”。焦らず、自分のペースで、本との対話を楽しんでみてください。
読んだ本をもっと楽しむ工夫

本を読み終えたあと、そのまま日常に戻ってしまうのは少しもったいない気がすることはありませんか。読書の楽しさは、読む時間だけでなく、その余韻をどう味わうかによっても深まっていきます。
ここでは、頑張りすぎずに取り入れられる、読んだ本をより楽しむための工夫について考えてみましょう。
ゆるくても記録をつけてみる
読書の楽しみは、読むときだけではありません。本を読み終えたあと、その余韻をどう過ごすかで、満足感がぐっと深まります。「せっかく読んだのに、すぐ忘れちゃう」と感じている人こそ、少しだけ“楽しみながら記録する工夫”を取り入れてみるのがおすすめです。
とはいえ「読書ノートをしっかり書かなくちゃ」「感想をまとめておかないと」そんなふうに思いすぎると、読書が“やらなきゃいけないこと”になってしまいます。
記録はもっとゆるくて大丈夫。たとえば、タイトルと日付だけメモする、心に残った一文を書き留める、あるいは気になったページをスマホでパッと撮る──そのくらいの軽さでOKです。
大事なのは、記録そのものではなく、「読んでよかったな」「この言葉、好きだな」と思えた瞬間を残しておくこと。気軽に続けられる記録法のほうが、結果的に長く楽しめます。
誰かに話すと記憶に残りやすい
本の感想を誰かに話すと、不思議と記憶に残りやすくなります。「この本にこんな場面があってね」と家族や友人に話したり、職場の同僚に「この一文が響いた」と伝えたり。たとえ一言でも口に出すことで、読書の余韻がより深まります。
また、SNSで「#読書記録」や「#今日の一冊」として軽くシェアするのもおすすめ。同じ本を読んでいる人から反応があると、「読書って楽しいな」と感じられます。人に話すことは、自分の感じ方を整理するきっかけにもなります。
読書をひとりだけのものにしない
読書はひとりの時間を楽しむものでもありますが、ときには“誰かとつながるきっかけ”にもなります。
たとえば、読書メーターなどのアプリで他の人の感想を読むと、自分とは違う視点に気づいたり、次に読みたい本が見つかったり。本屋さんや図書館のイベント、オンライン読書会などに参加してみるのも楽しい体験です。
誰かと感想を共有することで、本の世界がぐっと広がり、読書がより豊かであたたかい時間に変わっていきます。
読書習慣を作るためのステップ
読書を続けるコツは、いきなり完璧を目指さないこと。まずは“本に触れるきっかけ”をつくることから始めましょう。
・寝る前の10分だけ読む
・通勤電車で1ページ開く
・気になった本をスマホでメモする
そんな小さな積み重ねが、いつの間にか「読むのが当たり前」の習慣になります。本は、あなたのペースで寄り添ってくれる存在。焦らず、自分らしいリズムで“読む時間”を育てていきましょう。
読書は“少しずつ”が続けるコツ
読書は、たくさん読むことよりも、細く長く続けることが大切です。10分でも、1ページでも。今日読めなかったからといって、焦る必要はありません。
読書は「時間があるからするもの」ではなく、「日常の中に組み込むもの」。あなたのペースで、本との時間を楽しんでくださいね。